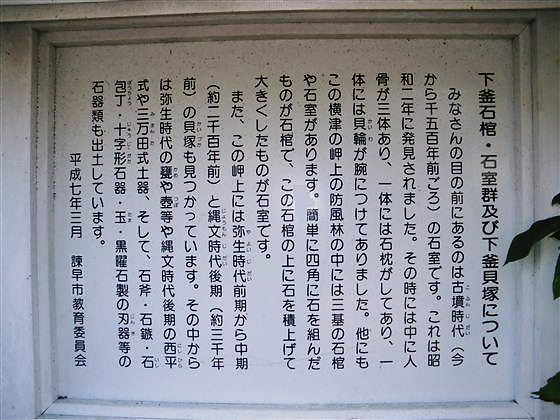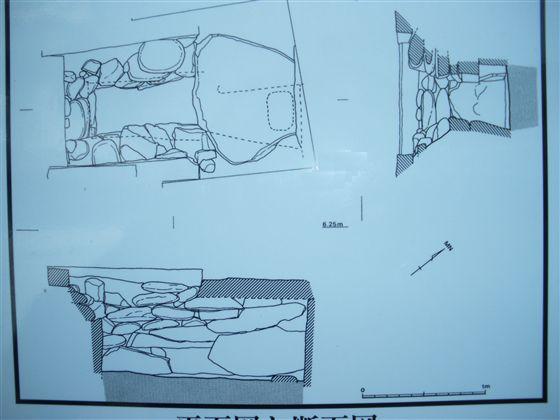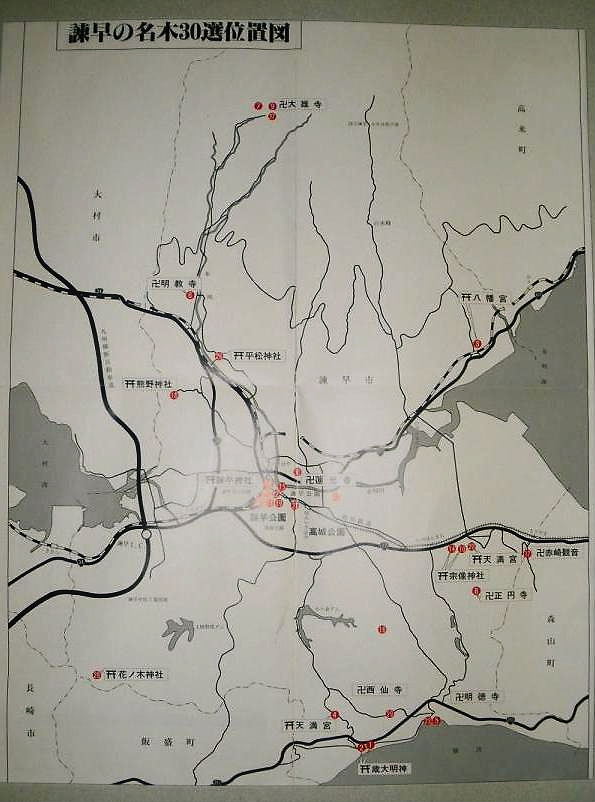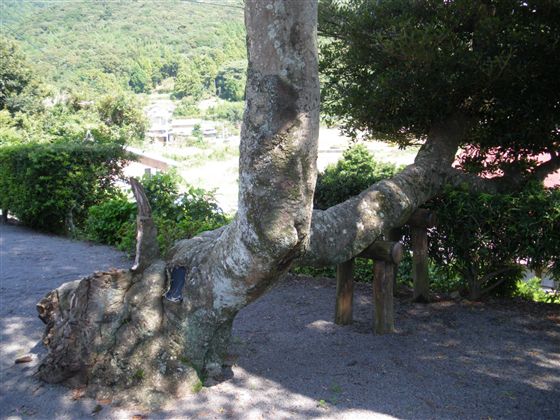正保4年長崎警備?「臼杵陣所」の標石が片淵で見つかる
長崎水道の明治33〜38年の第1回拡張事業で着工された本河内低部ダム−西山低部浄水場間の導水トンネルを訪ねていて、偶然に「片淵3丁目公民館」建物下でこの標石を見たのは、本年8月初めである。
参 照 https://misakimichi.com/archives/1203
1月半ほどそのままにしていたが、「役所」みたいな刻面だったので、貴重な標石と思われ、長崎楽会の中尾氏が近くの西山に住むため、標石の調査を頼んだ。
中尾氏がさっそく片淵3丁目公民館に標石を確認に行き、地元自治会で歴史に詳しい浦川大二郎さんから話を聞いてきてくれた。
標石の刻字は「臼杵陣所」。縦15cm、横18cm、高さ45cmの石柱。公民館左方の道路工事した5年ほど前、ショベルカーが掘り出した。長崎市文化財課に報告し、文献調査と保存を願い出たが、はっきりしたことがわからず、とりあえず公民館前に置いたまま、5年が経ったそうである。
中尾氏と浦川さんの推論では、この標石は、正保4年(1647)、2隻のポルトガル船が来航した時、長崎警備のため出陣した臼杵藩(大分県)が、この辺りの農家などを借り上げ、陣所を構えたものではないか、ということである。
江越弘人先生著「《トピックスで読む》 長崎の歴史」弦書房2007年刊の128〜129頁、同事件の解説は次のとおり。
「臼杵藩」が出陣したことが、まだはっきり確認できないが、標石の可能性としては、これが一番考えられる。
事件後、西日本の諸藩は、長崎に自前の蔵屋敷を設け、聞役を置き、長崎での情報を速やかに入手して、長崎出陣に備えるようになった。蔵屋敷を置いた藩は14に上がる。
佐賀藩では所領が長崎に隣接していたために、支藩(鹿島支藩)や大身の家臣(諫早領・深堀領)も自らの蔵屋敷を設けていた。
記録に表われない小藩があったかも知れない。当時の長崎警備の事件を思い起こさせる、まだ確証はないが、珍しい標石が掘り出されたのではないだろうか。
正保4年のポルトガル船入港(1647)
1640年、ポルトガルはおよそ60年振りにスペインから独立をかちとることが出来た。… 新しくポルトガル国王となったジョアン4世は、日本との通商の復活を願って、正保4年(1647)に、2隻の船でイスパニアからの分離を知らせる使節を送ってきた。
7年前の使節一行の処刑と使節船焼き捨ての記憶が、まだ生々しく残っていた。長崎港はたちまち緊張に包まれた。江戸へ早馬が飛び、九州各地から諸大名が兵を率いて続々と集結した。長崎港を取り巻く海岸や山々には5万の兵士が陣を敷き、港内には1500の兵船で埋まった。また、ポルトガル船が、勝手に出帆してしまわないようにと、港口の女神と男神(神崎)の間に船を並べ、その上に板を敷いて船橋を造り、港を閉鎖してしまった。
ポルトガル使節の船が、6月24日に入港してから、およそ1月後の7月28日には、上使の大目付井上筑後守と在府長崎奉行山崎権八郎が長崎に入ってきた。江戸から長崎間を15日で到着するという異例の早さであった。
会見は、早速翌日から始まった。筑後守は「来航してきた時には死刑をもって対応すると告げていたが、今回は、ポルトガル・イスパニアが分離したとの知らせの使節で、通商を願ってのことではないので、特にそのまま帰航することを許す。例え如何なることがあろうとも、再び来航することが無いように」と申し渡した。
こうして、今回は何事も無くポルトガル船は出港して行ったが、幕府にはさらに長崎警備の充実の必要性を痛感した。…