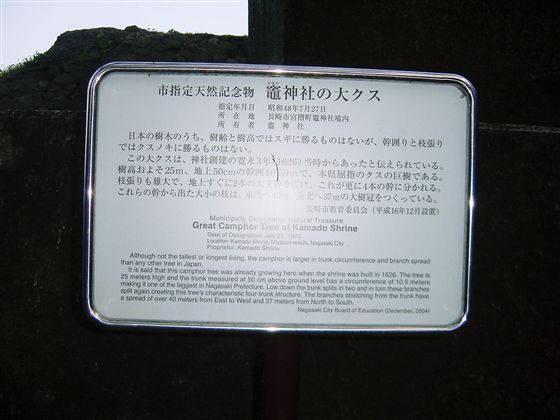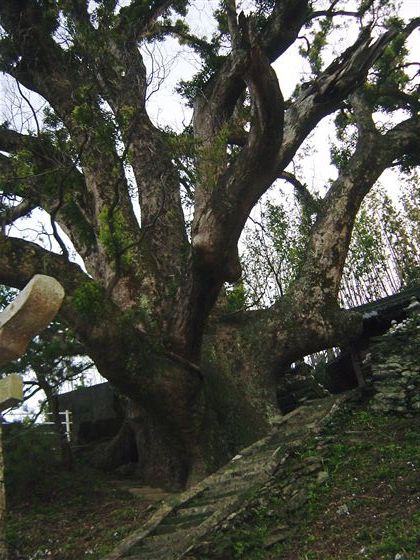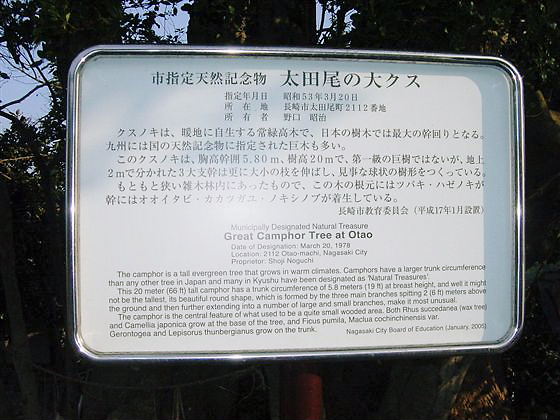田手原町重篭の「轟の滝」
田手原町重篭の下の沢に「轟の滝」という滝があることは聞いていたが、なかなか行くことはなかった。どんな滝か確かめたく、平成19年8月5日の午後訪ねた。甑岩や飯香浦に行くバス道路で重篭のバス停を過ぎ、最後の家の下のコーラ自販機のあるところから、右手へ下る車道分岐がある。この道は沢沿いに高速道早坂インター横に出る。
その途中、分岐から600mほど下ると、青フェンスのあるハウスが石垣上にあり、ここが滝道の下り口で、ゴーゴーと滝の音が聞こえ、こどもの手製か小さな標識があった。竹林の中を5分ほど下ると滝に出る。薄暗い沢。落差8mくらい。滝壺を有し、小さいながらまとまっている。下にも1段ある。長崎近郊では珍しい滝である。この沢は茂木若菜川の上流となる。
滝道途中には、茂木河平「戸町ヘ至ル」の標石のところで見た同じ「指指し」のコンクリート石柱があった。滝場は霊場で地蔵などが多く祀られ、滝の右手岩場には不動明王が立っていた。
HPの古書長崎銀河書房によると、長崎人文社刊「季刊・長崎人」17号(1998/1)に「長崎重篭の滝」の掲載記事があるが、確認していない。
なお、岩永弘著「歴史散歩 長崎東南の史跡」2006年春刊、63〜64頁が次のとおり紹介している。
(4)重篭・轟の滝
古書長崎名勝図絵に載っているのに辺鄙な所のため、知る人のみぞの感があります。バス停から150m先の右に下る農道を10分余り歩き、数本目の電信柱に記された718・ヒ341号の手前8mの所にある山道を200m下ると川があり、目前に滝があります。落差10m位。15体の石仏と儚き礎石が残っています。
伝 説
a:元禄15年(1703)田上の観音寺(私寺徳三寺の前身)開山・天州和尚が滝側に轟山観音寺普門院なる仏堂を建てた。いつの頃か毎夜一人の美女が堂上に現れ、怪異な事が起こり、このため住僧も恐れて逃げ出し、以来住む人も無く享保20年(1735)廃庵となった。
b:滝壺には神竜が潜み、旱魃の時、里人が祭り事を行い長竿で釣りの動作をして祈ると雨をもたらしたという。
c:二人の水練者が底を極めようとしたが達せず、一人は耳が聞こえなくなり、一人は髪が抜けてしまった。
「長崎名勝図絵」32頁の説明は次のとおり。
77 轟潭 とどろきのたき 衛鹿峰の東。川の源になっている。広さは僅かに二三歩であるが、深さは底知れない。その上から水が湧いて、小瀑布となってこの潭に落ちている。高さは十数仞。車のわだちのような音を立てて落ちるので、轟潭というのである。神龍が潜んでいると言伝えられ、霊異が多い。…以下は岩永氏紹介のとおり