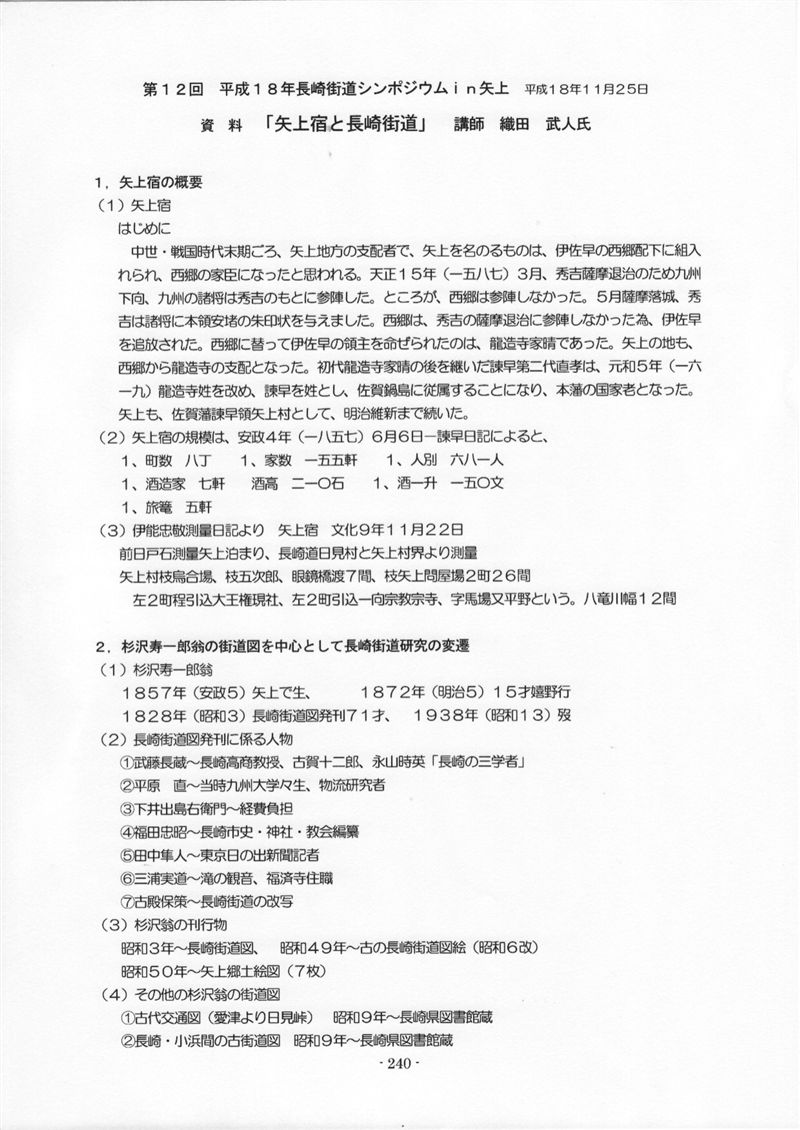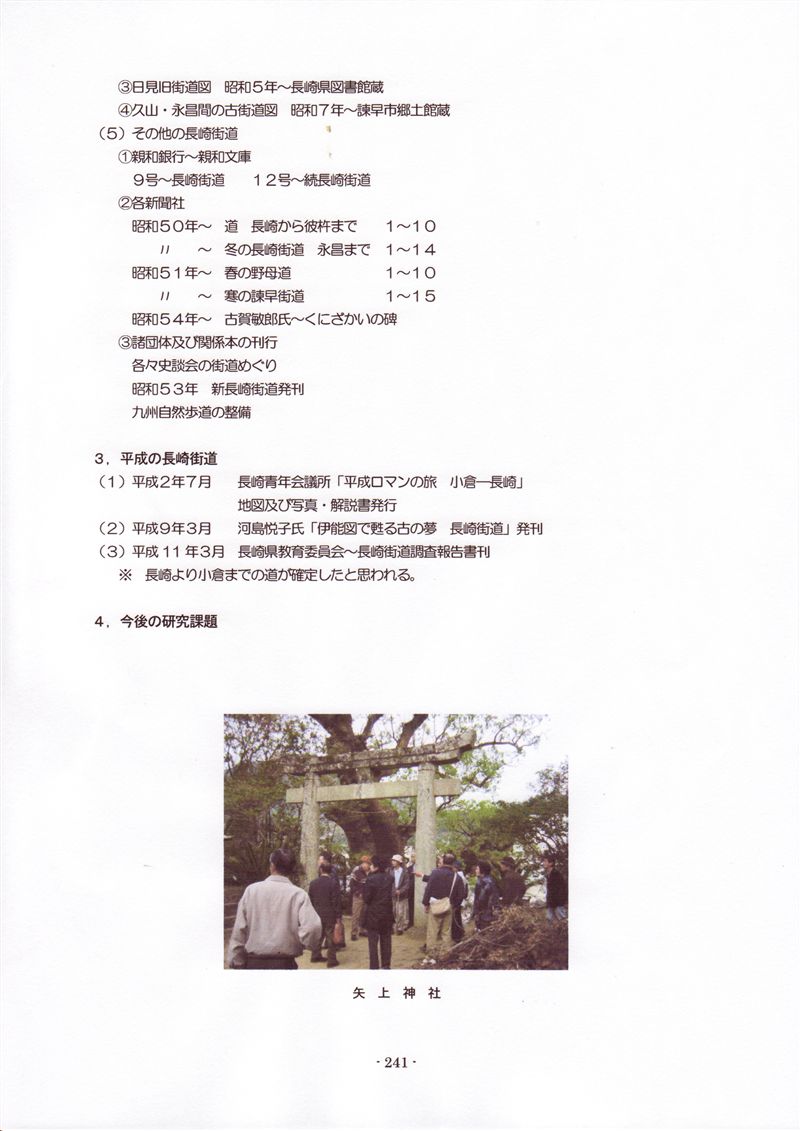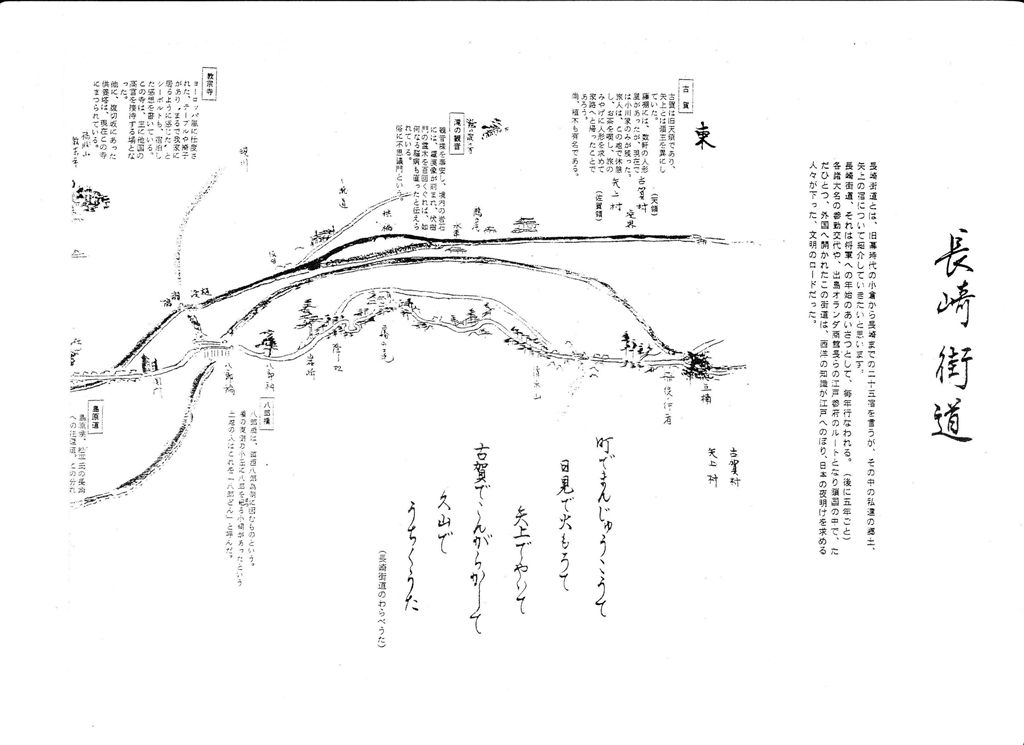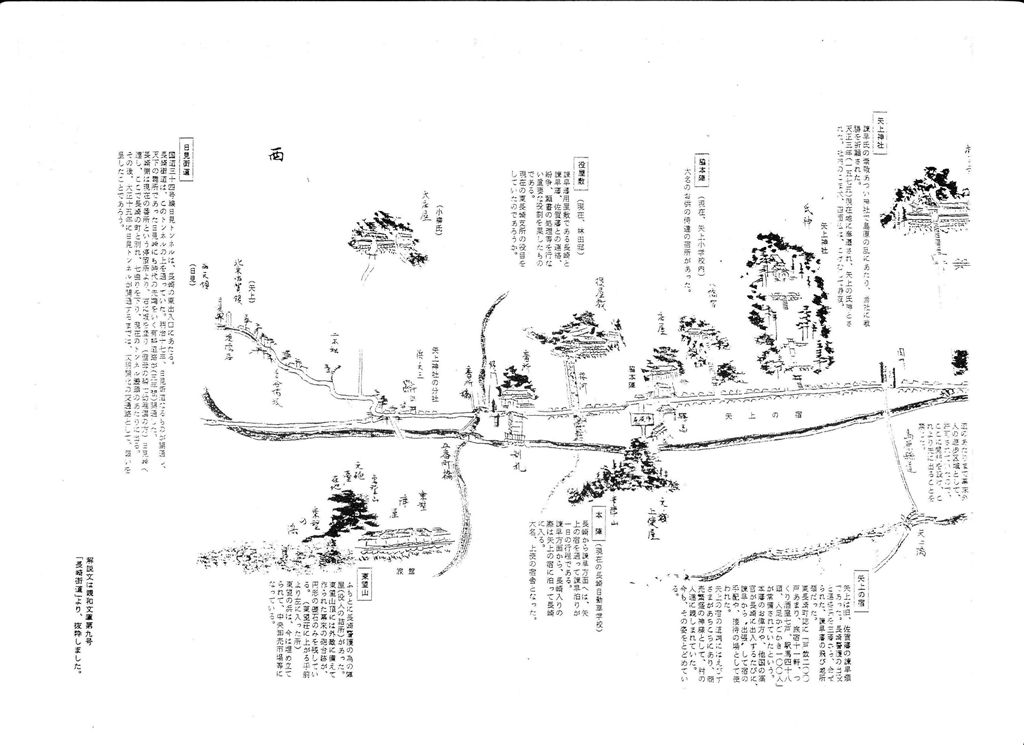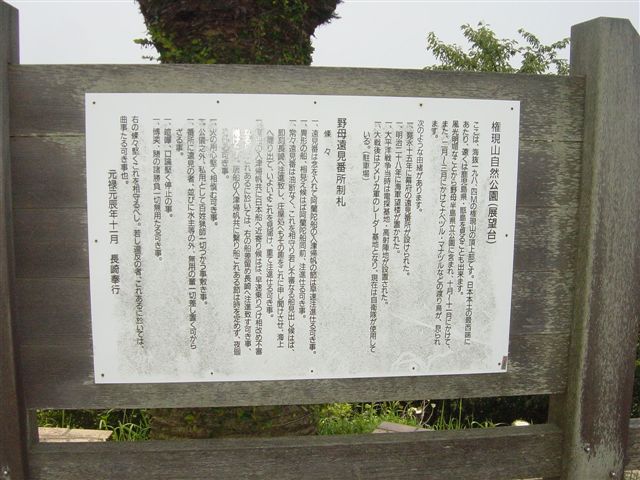豊前坊(飯盛神社)の両国力だめし石と蛤石
林正康先生の「長崎県の山歩き 新版」(葦書房2000年)豊前坊(標高340m)の項、18〜19頁に次のとおり紹介がある。
…石段を登ると、飯盛神社があります。社殿の背後の山は飯を盛った形をしているので、飯盛山といい長崎七高山の一つにあげられています。豊前坊というのは、英彦山にある社寺の豊前坊の名をもらったものです。…
社殿の左横には、両国梶之助土俵の力だめし石があります。地元本河内出身の両国関は、昭和三年(一九二八)、国技館で初土俵を踏み、小結、関脇と昇進し、十三年春には四八連勝中の横綱双葉山にうっちゃりをかませ、観客をわかせましたが、結局物言いがついて敗れました。
碑は「両国関初土俵力験之石 昭和二年十一月」とあり、石はその右の丸石であろう。
なお、両国碑の右側には、「蛤石」を飾っている。後の「蛤石の由来」碑文は次のとおり。
昔より当山に蛤石のあること傳説ありしが、昭和二十八年秋発見せり 此蛤石の頭をなで祈願すれば万病不思議になをる
昭和二十八年十月 発見者 五島作太郎ほか6名を連記 管理者 本河内町中
豊前坊(飯盛神社)へ行くには、田手原バス停先に案内標識があり、参道口の広場まで車が入ってすぐである。