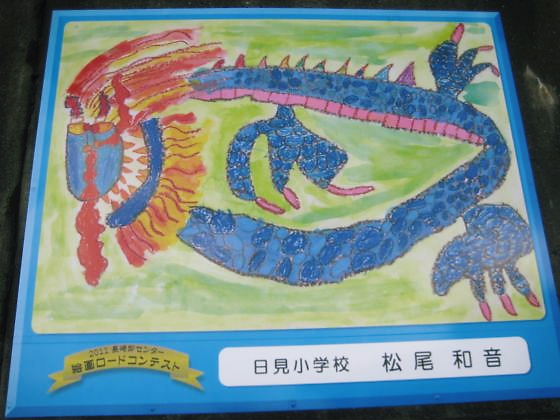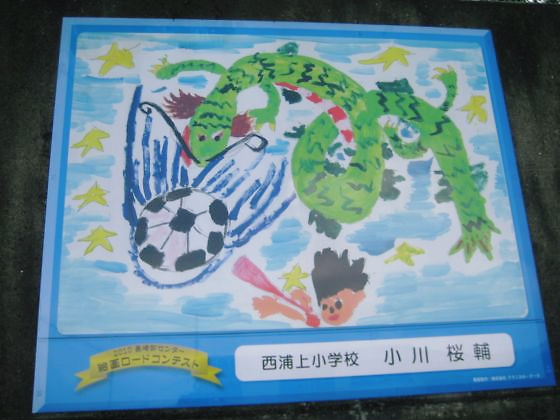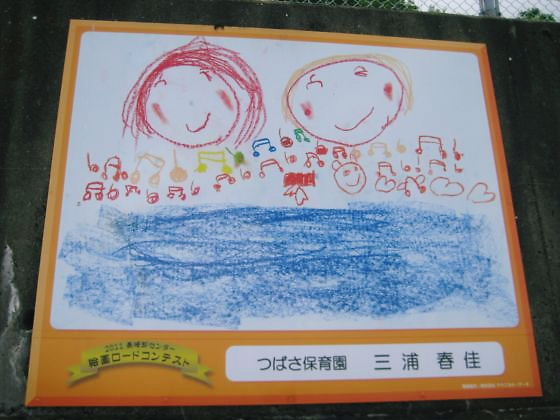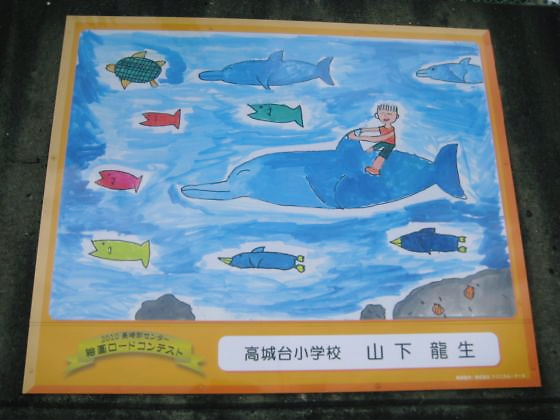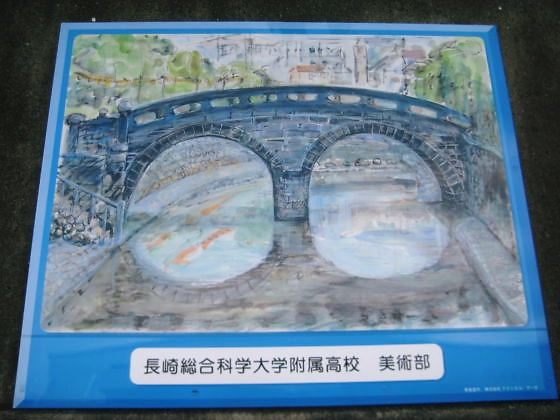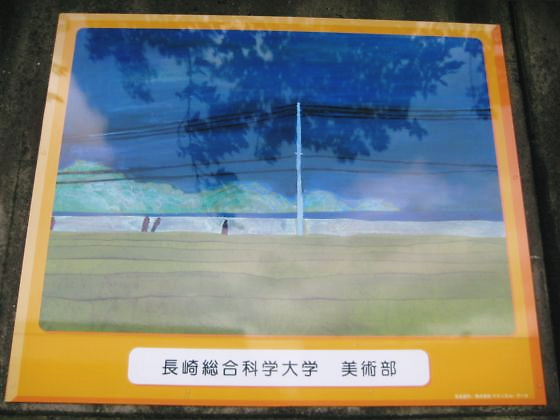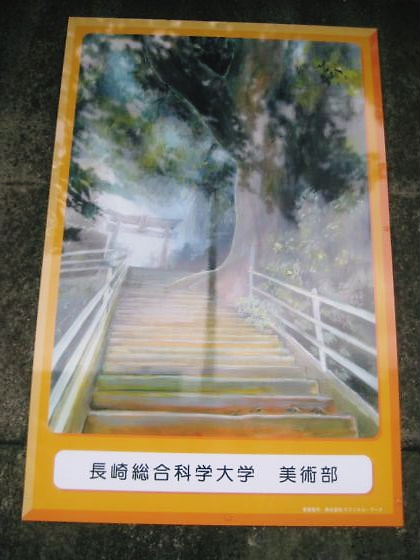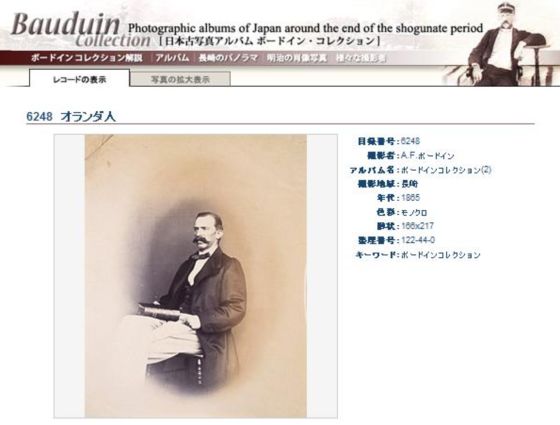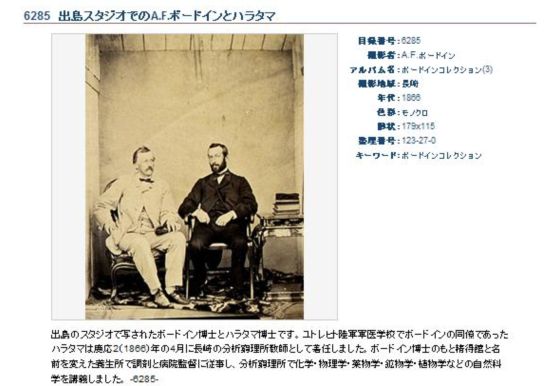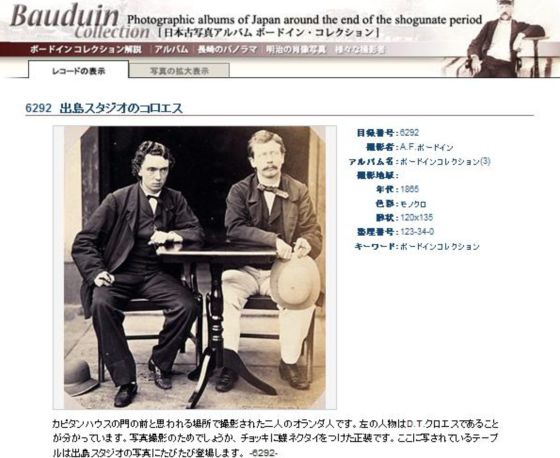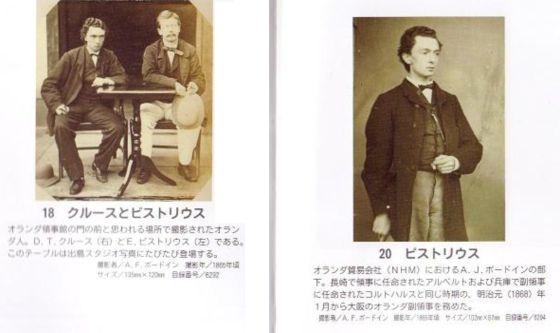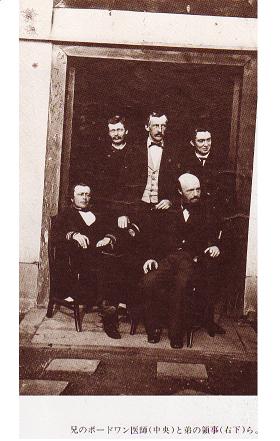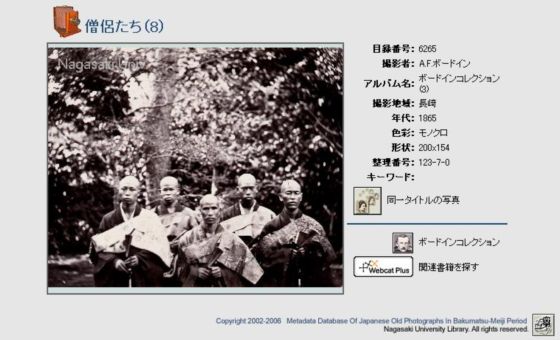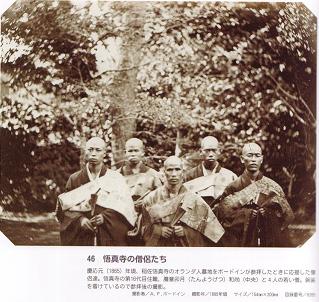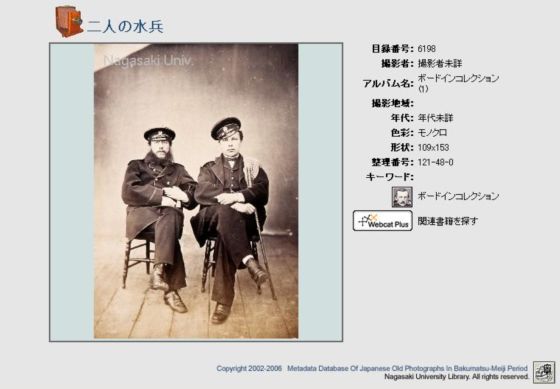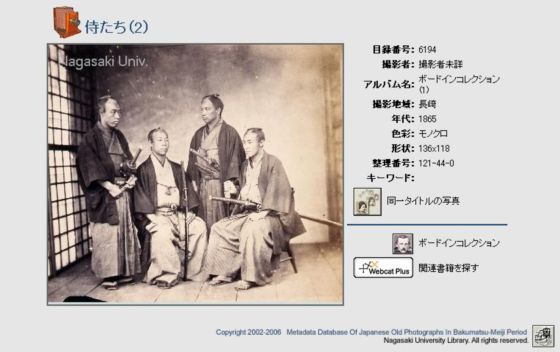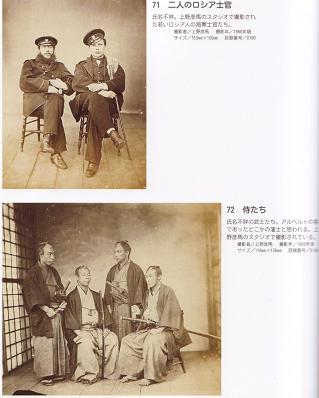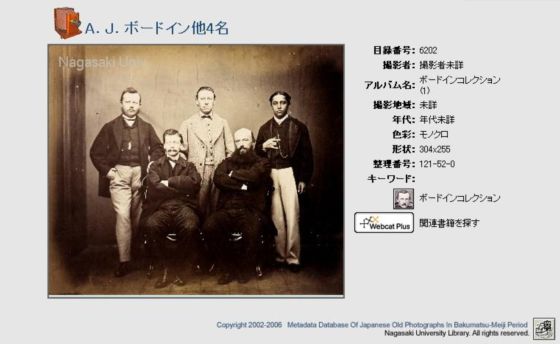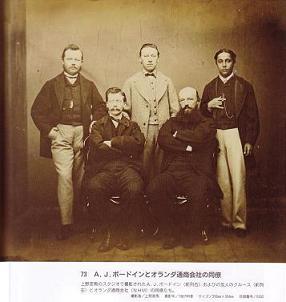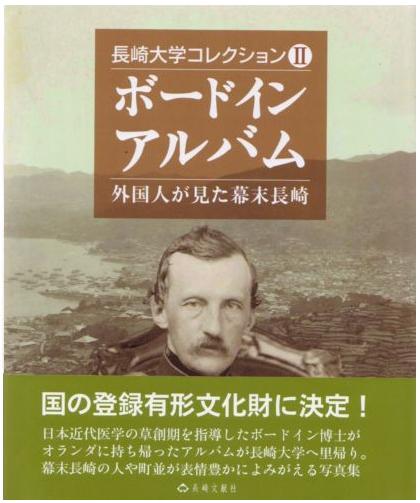伊方発電所 愛媛県西宇和郡伊方町
三崎港フェリーを降り、佐田岬半島の国道197号を東へ向かう。観光物産センター伊方きらら館の先に発電所の入口道路があった。近くまで下ると物々しい警戒であった。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による解説は、次のとおり。
伊方発電所
伊方発電所(いかたはつでんしょ)は、愛媛県西宇和郡伊方町にある四国電力の原子力発電所。
概 要 四国最西部、佐田岬半島付け根付近の北側斜面に位置し、瀬戸内海(伊予灘)に面している。四国電力および四国地方唯一の原子力発電所である。国内原発で唯一内海に面する。
状 況 福島第一原子力発電所事故の影響によって既に定期検査を終えた発電機も運転再開の目途が立たないため、全発電機が定期検査に入った2012年(平成24年)1月13日から送電を停止している[1]。
なお、伊方原発は「四国全体の電力の約4割以上をまかなう」と原発PRでされることがあるが、この数値は発電量ベースにて4割のことがあったというだけであり、実際の四国電力の設備容量では、「伊方原発の割合は2割余り」である[2]。
リスク 伊方原発の間近に巨大な活断層である中央構造線があり、将来大地震を引き起こす危険があることが、伊方原発訴訟にて原告から訴えられていた。ただし裁判当時の国内の地震学界では地震の活断層説には否定的な意見が占めており、受け入れられなかった[4]。
なお、最新の地震研究[5]によると中央構造線の伊方原発近くの活動は以下のように評価されている。
石鎚山脈北縁西部の川上断層から伊予灘の佐田岬北西沖に至る区間が活動すると、マグニチュード8.0程度もしくはそれ以上の地震が発生すると推定され、その際に2−3m程度の右横ずれが生じる可能性がある。
(中略)
石鎚山脈北縁西部の川上断層から伊予灘の佐田岬北西沖に至る区間は、今後30年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属することになる。
— 地震調査研究推進本部 地震調査委員会, 中央構造線断層帯(金剛山地東縁−伊予灘)の長期評価(一部改訂)について 平成23年2月18日