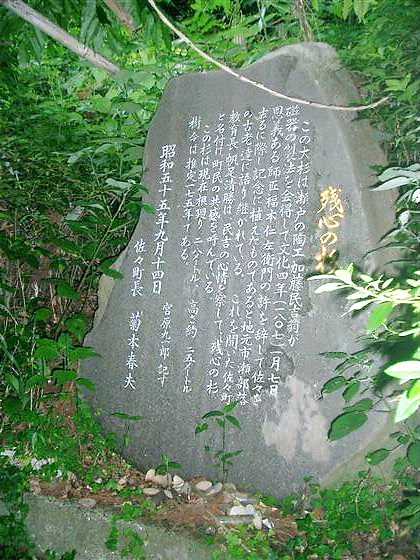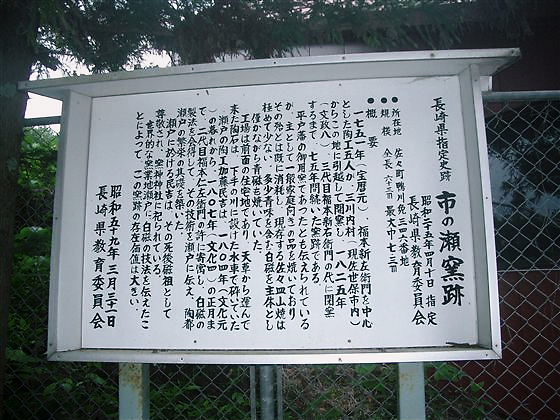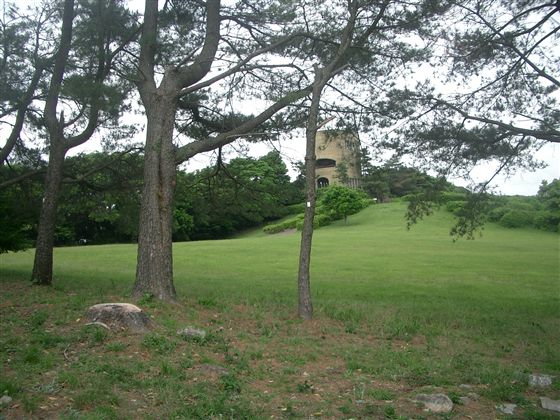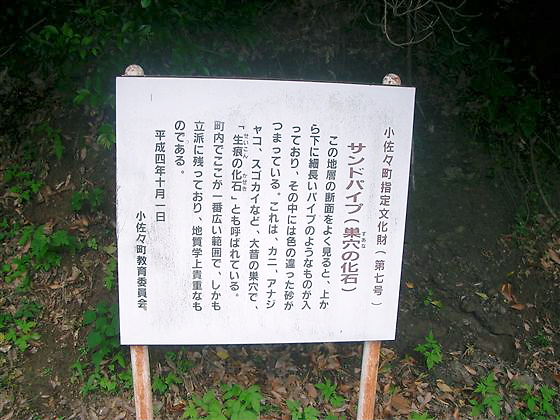昭和15年「海軍水準」の標石 小佐々町楠泊海岸で見かける
正面「海軍水準」、裏面「水路部」、右面「+」、左面「昭和十五年」。下部は埋れて不明。
「海軍水準」とは珍しい。陸軍省「要塞地帯(区域)標」は長崎市内の海岸でよく探し見つけたが、初めて目にする境界石以外の海軍標石を、佐世保市小佐々町楠泊の海岸で見かけた。
佐世保市小佐々行政センター近く「田原」交差点から、県道18号線により冷水岳へ向かった。小佐々中学校からカーブの多い坂道を下ると、楠泊漁港へ出る。冷水岳への登山道路は大橋の手前にあるが、前面の島々の写真を写すため、塗装工事中の大橋を渡った。
集落先の海岸突端に、大きな鳥居が数本見える。弁当をそろそろとここへ向かった。煮干の臭い波止場加工場の中を通り、突端に出た。
恵比須神社と思っていたら、大きな鳥居が3本あり扁額に「姫神社」とある。石段を登った上の社殿も立派だった。石段の登り口左には、別の「西宮神社」が祀られ、石祠2基があった。さすが漁業の町だ。
弁当を空にし、西宮神社鳥居下の海岸を歩いた。すぐ足元にこの標石があった。
三角点は方角を示す「+」があり、水準点は、上部に丸型の凹凸があるものがほとんどである。しかし、この標石は右面に「+」がある。やはり、「十号」だろうか。白御影石造り。一等三角点の大きさだ。とりあえず写真に写した。
今も使われているのだろうか。根元はしっかりコンクリートにより固められていた。
今、HPにより「水準点」を調べている。見たかぎり「海軍」に該当するものや、同じような標石は表われてこない。写真が全くないから困った。
海上保安庁に尋ねるか、近代測量史研究の京都市上西先生へ知らせて、またお願いするしかない。
(追 記) 京都市上西先生からの平成20年6月6日返信は次のとおり。
一般的に水路部の標石は要塞境界標などと異なり海図のために民間にも役立つよう設置されているものが多いようです。陸地測量部(国土地理院)の水準点は道路沿いのものが多いですが水路部は海岸で多くありません。
また水準路線は陸地測量部の路線と結合するようになっているはずです。水位(潮位)の基準となるものと思います。現在は標石ではありませんが金属標がつかわれており「水路測量標」と呼ばれます。所管は海上保安庁海洋情報部で根拠法律は水路業務法です。
それにしても水路部の「海軍水準」と刻字のある標石は、わたしはまだ見たことがありません。壱岐島の嶽ノ峯(だけのつじ)の一等三角点脇には「緯度測定標」「水路部」「明治廿二年三月」の刻字ある標石があるそうですが、これもまだ見ておりません。
(追 記) 京都市上西先生からの平成20年9月28日返信は次のとおり。
このたびは嶽ノ峯の水路部緯度測定標の情報をいただきありがとうございました。同標石が健在であることが確認できました。全国で数少ない水路部の標石ですので大切にしたいと思っております。ご存知のとおり浜田の標石は撤去されて既になくなっています。わたしの探訪したのは小樽、秋田、出雲崎の3ヶ所のみです。
過日、お知らせいただいた小佐々町の海軍水準標石は同様なものが全国各地にあったようですが現存が確認できているのは小佐々町のみで「海軍」と刻字があるのは珍しいようです。+印は+の横棒が測定位置になり、この横棒を基準として海面の比高値を求めます。現行のものは標石でなくすべて金属標になっており水平に設置された金属標の頭を基準とします。海図にはHBMとして載っています。この金属標はわたしも敦賀でみたことがあります。