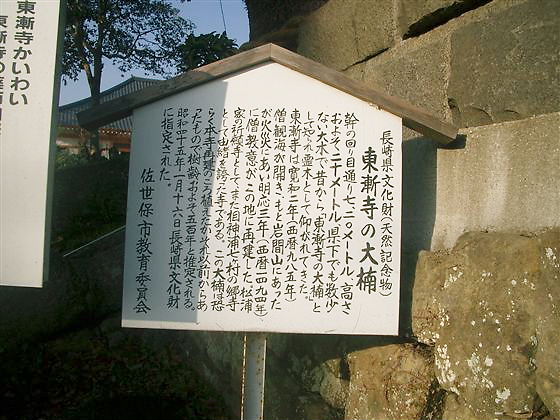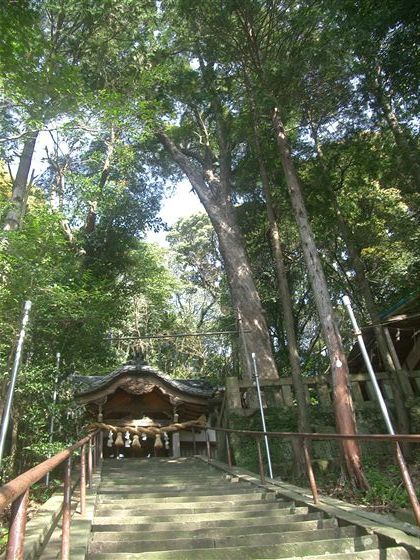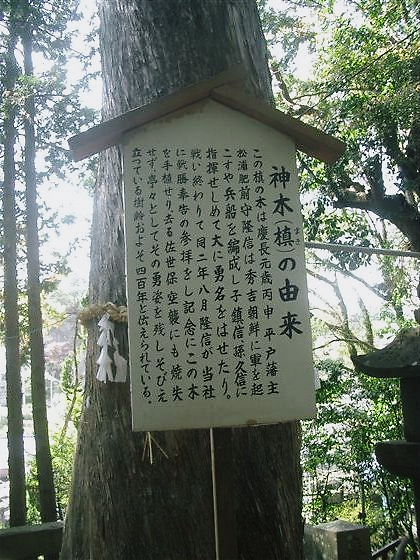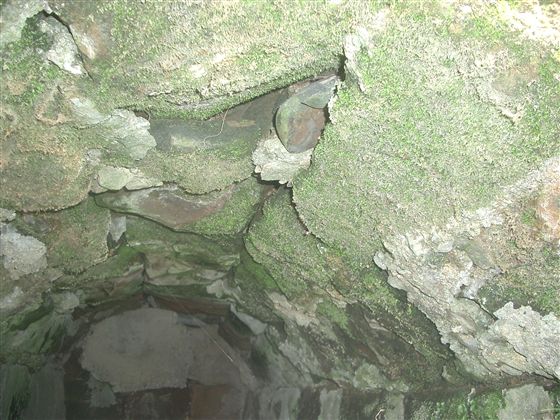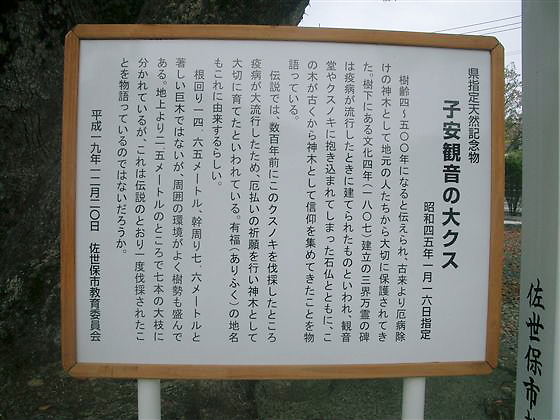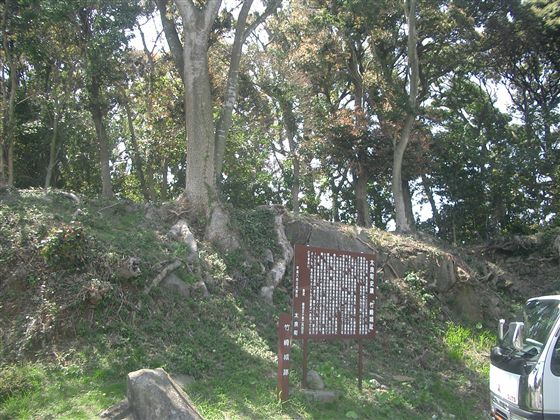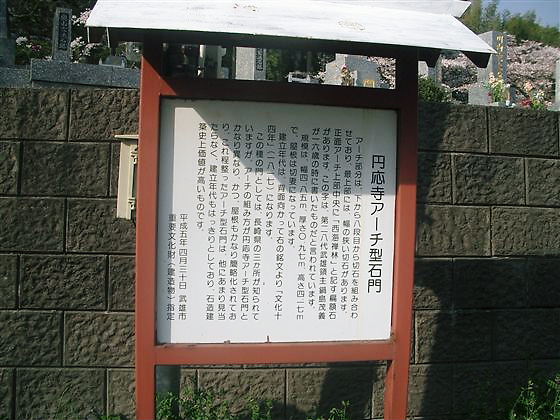三川内山の早川小学校跡に残る小さなアーチ石橋 佐世保市塩浸町
平成20年4月12日、佐世保市三川内山の石橋を訪ねた。陶芸の里「三川内皿山」はJR三河内駅手前、国道35号線三川内山入口交差点から右折し、奥の谷間へ入る。
三川内山の石橋は、「三川内山」バス終点児童公園下の川に残り、すぐ手前の路地から右へ下る。陶石色の見事なアーチ石橋である。
これと別に私が見かけた小さな石橋は、国道から皿山へ行く中間くらいの所。市立三川内山保育所とバス停がある。この手前右方の3軒の民家へ車道からコンクリート舗装道が下って上がっている。道が小川を跨いでいるので、皿山の帰りに寄って調べてみた。
写真のとおり可愛いアーチ石橋が残っていた。上にコンクリートが塗られている。左面から見えるが、右面からは拡幅されて確認できない。幅2m、長さ1mほどの小橋。
礎石や石の組み方からアーチ石橋としてカウントできないかも知れないが、石橋があった報告をしてみたい。
橋の道は、上の2軒の邸宅の登り口。事情を手前の林田宅へ聞いてみた。この高台は今は家と庭畑となっているが、実は三川内小学校発祥之地「早川小学校跡」である。
昭和49年2月、創立100周年を記念し山口造園代表取締役山口廣夫氏が寄贈した記念碑があり、早川小学校がここにあったのは、「自 明治十二年三月 至 明治十九年九月」と刻んでいた。左への道奥木立には祠が祀られていた。
どうやら石橋は、早川小学校創立時に造られた学校正門口の橋のようであり、小さいながら地元三川内山の貴重な歴史を残した橋ではないだろうか。
なお、最後の2枚の写真は、バス終点の「三川内山案内」と、すぐ近くこれまで紹介されている「三川内山の石橋」。