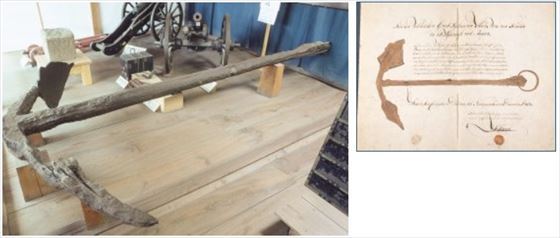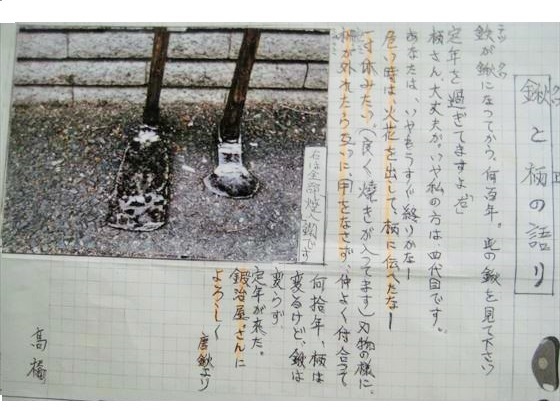長刀岩台場・跡 長崎市香焼町
サイト「近世以前の土木・産業遺産」長崎県リストによるデータは、次のとおり。現地は三菱香焼ドックのため立ち入りできないので、海上からの撮影。
長刀岩台場・跡 なぎなたいわ
長崎市 香焼町 台場 (新台場・増台場) 文化5-7(1808-10) 市教委 立入禁止(海岸沿いにあり船から石垣がよく見える)/三・四ノ増台場跡、常住小屋跡の石垣が残存 古台場は肥前・平戸藩、増台場は筑前・福岡藩が構築(新台場は不明)/旧香焼島の北端・長刀鼻に設置 3 B
2007年、知人の釣り船で近くの高鉾島に上陸調査後、香焼島にも接近し写した。「長刀岩台場」の詳しい文献はわからないが、場所はここであろう。
国史跡「魚見岳長崎台場跡」に、本年3月「四郎ヶ島台場跡」が追加指定された。佐賀藩が同時に築いた香焼島「長刀岩台場」や「伊王島の各台場」が指定からもれている。
特に伊王島灯台下の「出鼻(又は真鼻)台場跡」の荒れ方はひどい。旧伊王島町や長崎市が、展望台や東屋を造っている。保存状態が悪かったから、指定できなかったのだろうか。
山口広助氏のHP”広助の『丸山歴史散歩』”による説明は、次のとおり。
C-530:長刀台場跡(なぎなただいば-あと) ●2012/01/12
香焼町(香焼村字蔭ノ尾)【三菱香焼工場】
寛永16年(1639)ポルトガル船の日本渡航を禁止し鎖国が完成。しかし正保4年(1647)ポルトガル船が通商再開を請うため来航し長崎港は緊張が走ります。翌年の慶安元年(1648)西泊戸町番所を増強し、承応2年(1653)幕府は平戸藩松浦肥前守鎮信に命じ長崎港内7か所に台場を設けます。このうち4か所は長崎港外に設けられ、蔭ノ尾島の北、長刀岩に設けられ侵入の船を警戒していました。この台場は旧蔭の尾灯台一帯にあったものと考えられていて、文化5-7年(1808-10)には増台場が増築。さらに駐屯小屋が上下2段の平地に設けられ、石垣と大井戸が現存しています。
(2014年12月4日 追 記)
以下は、入江氏からの協力画像を末尾に追加して載せる。
香焼島の内、蔭ノ尾島に在った長刀岩台場と蔭ノ尾島の位置を航空写真に書き込みました。長刀岩台場は海岸近くが在来台場、その一段上に四番、その上に三番、二番、一番と高い場所に造られました。
蔭ノ尾は陰ノ尾とも書かれている台場で、海岸に在来台場、崖の上に新規台場が造られました。
添付した写真「長刀陰ノ尾台場1」はYahooの航空写真です。
「長刀陰ノ尾台場2」は国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」整理番号MKU628、1962年5月29日撮影の写真です。